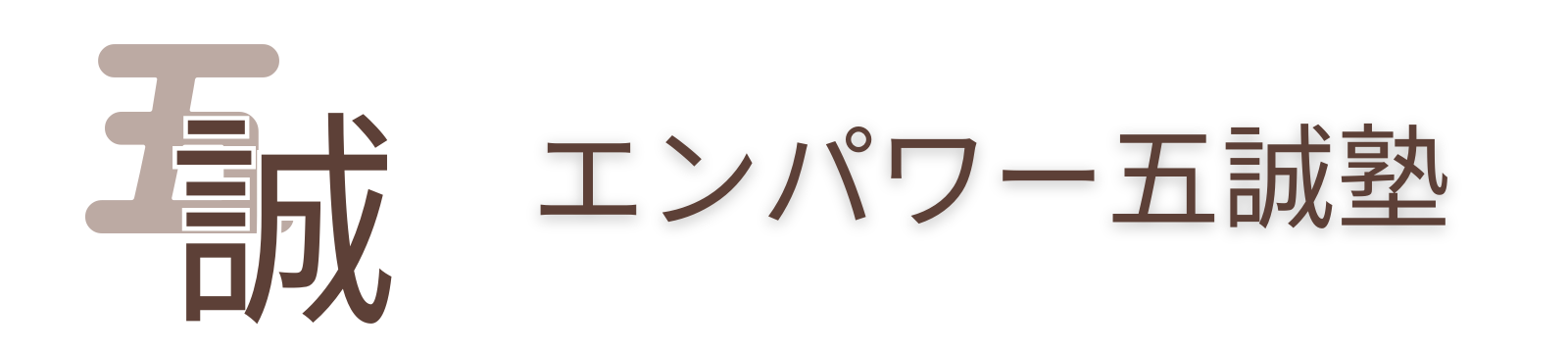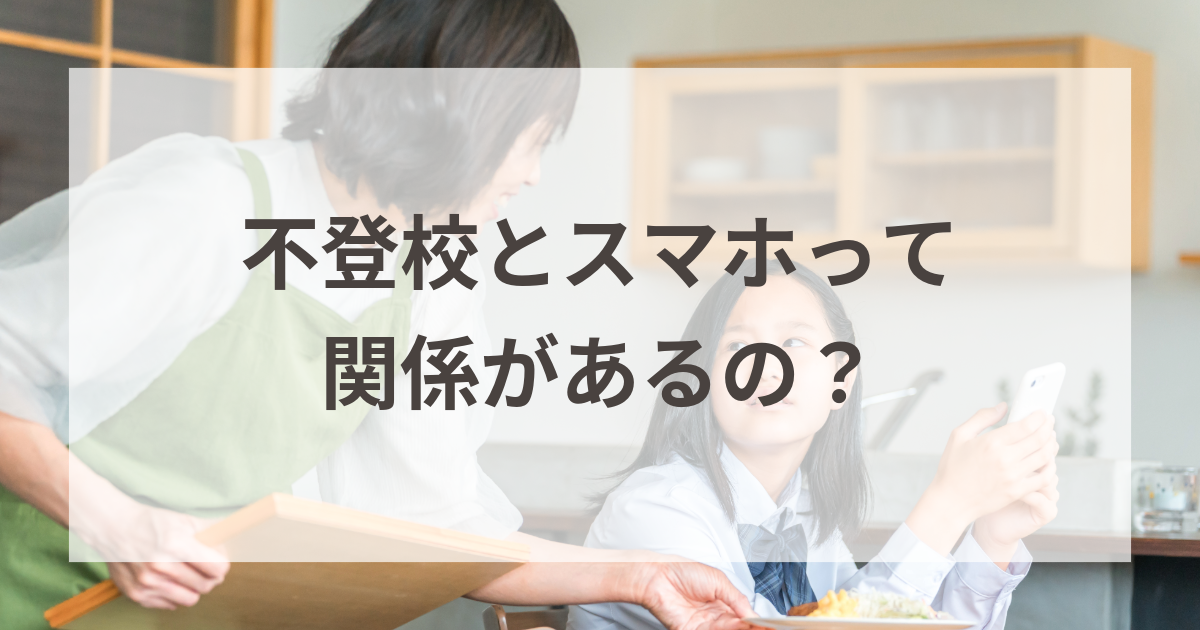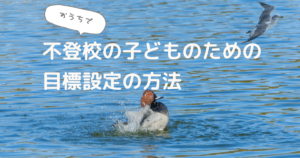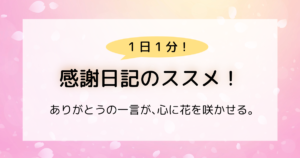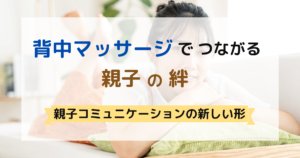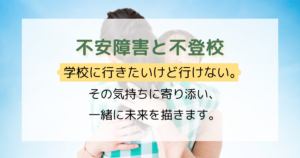こんにちは。
子どものスマホで悩んでいませんか?
「うちの子、一日中スマホばかり見ていて学校に行かない…」
「スマホを取り上げたら、もっと状態が悪化するのでは…」
不登校のお子さんを持つ保護者の方から、このようなお悩みが増えてきています。
スマホの長時間利用と不登校。
一見、スマホの使用と不登校が関連しているように思えますが、この二つを結びつけ、
単純に「スマホ依存が原因だ」と結論づけてしまうのは、実は問題の本質を間違ってしまうことがあります。
この記事では、多くの不登校のお子さんの体に触れてきた整体師の視点から、スマホが子どもの心身に与える本当の影響と、不登校との根深い関係を解説します。
そして、ご家庭で実践できる具体的な3つの対策をご紹介します。お子さんの体の不調に気づき、適切にアプローチすることで、状況が好転するきっかけが見つかるかもしれません。
不登校とスマホ、単純な「使いすぎ」で片付けていませんか?
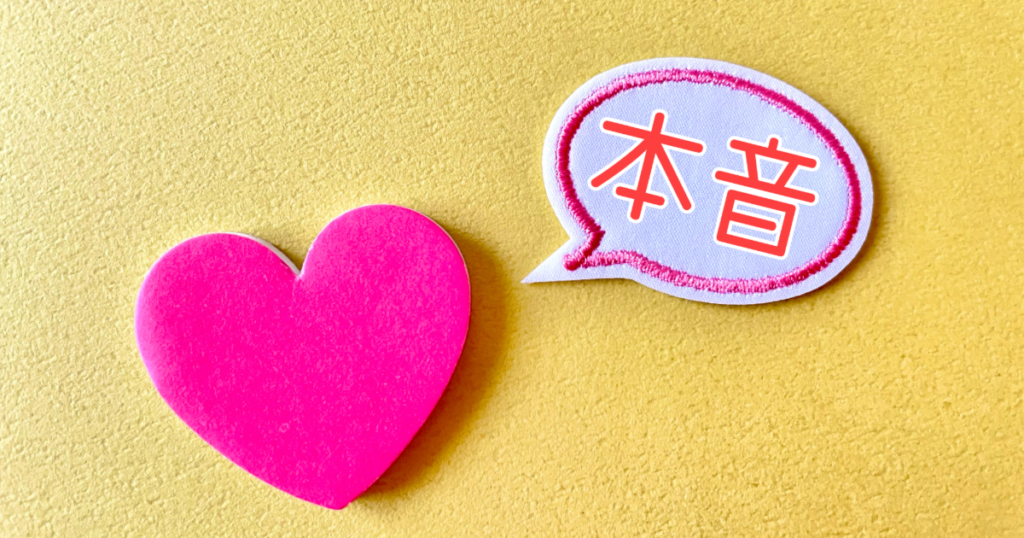
多くの方が「スマホの使いすぎで昼夜逆転し、学校に行けなくなった」と考えがちです。
しかし、体の専門家として多くのお子さんを見てきた経験から言うと、順番が逆であるケースも多々あります。
「スマホが原因で不登校」ではなく「不登校だからスマホに没頭する」?
学校生活における人間関係や勉強、環境の変化は、子どもの体に様々なストレスを与え、心と体のエネルギーが無くなっていき、
「学校に行きたくても行けない」
状態が不登校の始まりと言われています。
子どもは一人ぼっちになっていると感じる心細さ、そして現実からの逃避、社会との唯一のつながりを求めて、スマホへと逃げ場(居場所)を求めていきます。
つまり、
スマホは「原因」というよりも、エネルギーが尽きてしまった子どもがたどり着く「避難場所」になっていることが多いのです。
ですから、頭ごなしにスマホを否定したり取り上げたりすることは、子どもの唯一の居場所を奪い、親子関係を悪化させるだけになりかねません。
【整体師の視点】スマホが子どもの心身を蝕む3つのメカニズム

なぜスマホに没頭することが、不登校からの回復を妨げてしまうのでしょうか。そこには、整体師だからこそわかる「3つの体の問題」が深く関わっています。
スマホ首とは、スマホを見るときの「うつむき姿勢」を言います。
スマホを使っているとき、どうしても下向きの姿勢になります。
下向きの状態が続くと、首の骨(頸椎)の自然なカーブが失われる「ストレートネック」、通称「スマホ首」になります。
スマホ首で首周りの筋肉がガチガチに固まると、脳へ送られる血流が悪化します。
さらに重要なのは、首には心と体をコントロールする「自律神経」の束が通っています。スマホ首が続くと自律神経の働きに大きく影響を与えます。
それが感情の乱れにつながっていくのです。
スマホ画面から発せられるブルーライトが、睡眠に悪影響を与えると言われています。人間の体は、夜になると自然な眠りを誘う「メラトニン」というホルモンが分泌されます。
しかし、夜間に強い光であるブルーライトを浴び続けると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。
これにより、
- 寝つきが悪くなる
- 眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める
- 朝、すっきりと起きられない
という状態に陥ります。
これが、不登校の子どもに多い「昼夜逆転」の大きな原因の一つです。
スマホを見るときの猫背の姿勢は、首だけでなく胸周りにも影響します。
背中が丸まり、肩が内側に入ることで、肋骨の動きが制限され、肺が十分に広がらなくなります。
その結果、無意識のうちに「呼吸が浅く」なってしまうのです。
浅い呼吸は、自律神経のうち交感神経を優位にし、心身をさらに緊張させます。また、体内に十分な酸素を取り込めないと、全身の細胞が酸欠状態になり、
- 慢性的な疲労感
- 集中力の低下
- 気分の落ち込み、無気力
スマホ首は上記のような症状につながっていきます。
親としてどう向き合う?家庭でできる3つの具体的アプローチ
- 対策①:ルール作りより「体のケア」を優先する
- 対策②:睡眠環境を整え、体内時計をリセットする
- 対策③:スマホ以外の「楽しい」「安心できる」時間を作る
スマホと不登校対策①:ルール作りより「体のケア」を優先する
「スマホは1日1時間まで」といったルール作りから入ると、子どもは反発しがちです。
それよりも先に、
「なんだか最近体がしんどそうだね」と、
体の心配、ケアからアプローチするのも1つの方法です。
たった一言の声かけで、子どもの気持ちは変わっていきます。
スマホと不登校対策②:睡眠環境を整え、体内時計をリセットする
質の良い睡眠は、心身の回復に不可欠です。物理的にブルーライトを遠ざける工夫をしましょう。
- 寝る1〜2時間前はスマホを見ない: 「寝室にスマホを持ち込まない」「充電はリビングでする」など、家族の中でのルールを作るとよいです。
- 寝室の室温を調節する: 寝室の室温は夏は26度前後、冬は20度前後がおすすめです。そして湿度も重要です。湿度は60%程度を目安に調節するとよいです。
スマホと不登校対策③:スマホ以外の「安心できる」時間を作る
はい、承知いたしました。「スマホの使用時間と不登校の関係」について、整体師の観点を取り入れたブログ記事を2000文字程度で作成します。SEOを意識し、検索意図、ターゲット、キーワードを考慮した構成で作成します。
【整体師が解説】不登校とスマホの深い関係。姿勢の乱れが自律神経を乱す?親ができる3つの対策
導入文
「うちの子、一日中スマホばかり見ていて学校に行かない…」 「スマホを取り上げたら、もっと状態が悪化するのでは…」 不登校のお子さんを持つ保護者の方から、このようなお悩みを伺うことが増えました。スマホの長時間利用と不登校。この二つを結びつけ、単純に「スマホ依存が原因だ」と結論づけてしまうのは、実は問題の本質を見誤っているかもしれません。 この記事では、多くの不登校のお子さんの体に触れてきた整体師の視点から、スマホが子どもの心身に与える本当の影響と、不登校との根深い関係を解説します。そして、ご家庭で実践できる具体的な3つの対策をご紹介します。お子さんの体の不調に気づき、適切にアプローチすることで、状況が好転するきっかけが見つかるかもしれません。
不登校とスマホ、単純な「使いすぎ」で片付けていませんか?
多くの方が「スマホの使いすぎで昼夜逆転し、学校に行けなくなった」と考えがちです。しかし、体の専門家として多くのお子さんを見てきた経験から言うと、順番が逆であるケースも少なくありません。
「スマホが原因で不登行」ではなく「不登校だからスマホに没頭する」
そもそも、学校生活における人間関係や勉強、環境の変化など、様々なストレスによって心と体のエネルギーが枯渇し、「学校に行きたくても行けない」状態になっているのが不登校の始まりです。 その心細さや現実からの逃避、社会との唯一のつながりを求めて、子どもはスマホの世界に救いを求めます。つまり、スマホは「原因」というよりも、エネルギーが尽きてしまった子どもがたどり着く「避難場所」になっていることが多いのです。 ですから、頭ごなしにスマホを否定したり取り上げたりすることは、子どもの唯一の居場所を奪い、親子関係を悪化させるだけになりかねません。
【整体師の視点】スマホが子どもの心身を蝕む3つのメカニズム
では、なぜスマホに没頭することが、不登校からの回復を妨げてしまうのでしょうか。そこには、整体師だからこそわかる「体の構造的な問題」が深く関わっています。
① 「スマホ首」が引き起こす自律神経の乱れ
最も深刻な問題が、スマホを見るときの「うつむき姿勢」です。人間の頭の重さは約5〜6kg。ボーリングの球ほどの重さがあります。首を30度傾けるだけで、首にかかる負担は18kgにもなると言われています。 この状態が続くと、首の骨(頸椎)の自然なカーブが失われる「ストレートネック」、通称**「スマホ首」**になります。
このスマホ首が万病のもとです。首周りの筋肉がガチガチに固まると、脳へ送られる血流が悪化します。さらに重要なのは、首には心と体をコントロールする**「自律神経」**の束が通っていることです。 筋肉の緊張によって自律神経が圧迫されると、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」のスイッチがうまく切り替わらなくなります。特に交感神経が過剰に優位な状態が続き、常に体が緊張・興奮状態に。その結果、
- イライラ、不安感
- 原因不明の頭痛、めまい、吐き気
- 慢性的なだるさ、倦怠感
- 不眠 といった、まさに不登校の子どもたちに多く見られる症状が引き起こされるのです。
② ブルーライトによる「睡眠の質」の低下と昼夜逆転
スマホ画面から発せられるブルーライトが、睡眠に悪影響を与えることは広く知られています。私たちの体は、夜になると自然な眠りを誘う「メラトニン」というホルモンを分泌します。しかし、夜間に強い光であるブルーライトを浴び続けると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。 これにより、
- 寝つきが悪くなる
- 眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める
- 朝、すっきりと起きられない という状態に陥ります。これが、不登校の子どもに多い「昼夜逆転」の大きな原因の一つです。睡眠の質が低下すると、日中の活動エネルギーが回復しないだけでなく、脳の機能も低下し、思考力や感情のコントロールが難しくなります。
③ 姿勢の悪化が招く「呼吸の浅さ」と気分の落ち込み
スマホを見るときの猫背の姿勢は、首だけでなく胸周りにも影響します。背中が丸まり、肩が内側に入ることで、肋骨の動きが制限され、肺が十分に広がらなくなります。 その結果、無意識のうちに**「呼吸が浅く」**なってしまうのです。
浅い呼吸は、自律神経のうち交感神経を優位にし、心身をさらに緊張させます。また、体内に十分な酸素を取り込めないと、全身の細胞が酸欠状態になり、
- 慢性的な疲労感
- 集中力の低下
- 気分の落ち込み、無気力 といった症状につながります。整体の観点では、深い呼吸ができない体は、精神的にも不安定になりやすいと考えます。うつむき姿勢で浅い呼吸をしながら、ポジティブな気持ちになるのは非常に難しいのです。
親としてどう向き合う?家庭でできる3つの具体的アプローチ

お子さんの不登校とスマホの問題の背景に、体の不調があることをご理解いただけたでしょうか。ここでは、ご家庭でできる具体的な対策を3つのステップでご紹介します。
対策①:ルール作りより「体のケア」を優先する
「スマホは1日1時間まで」といったルール作りから入ると、子どもは反発しがちです。それよりも先に、「なんだか体がしんどそうだね。少し楽になるストレッチを一緒にやってみない?」と、体のケアからアプローチしてみましょう。 親子で一緒にできる簡単なストレッチがおすすめです。
- 首のストレッチ: ゆっくりと首を前後左右に倒し、じんわりと伸ばします。回すときはゆっくりと、痛みが出ない範囲で行いましょう。
- 肩甲骨はがし: 両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように前回し・後ろ回しを各10回行います。肩甲骨が動くのを感じるのがポイントです。
- 胸を開くストレッチ: 両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せながら胸をぐーっと開きます。浅くなった呼吸を深くする効果があります。
こうしたケアを日常に取り入れることで、お子さん自身も「スマホばかり見ていると体が凝るな」と自覚するきっかけになります。専門の整体院などで体の歪みをチェックしてもらうのも有効な手段です。
対策②:睡眠環境を整え、体内時計をリセットする
質の良い睡眠は、心身の回復に不可欠です。物理的にブルーライトを遠ざける工夫をしましょう。
- 寝る1〜2時間前はスマホを見ない: 「寝室にスマホを持ち込まない」「充電はリビングでする」など、家族共通のルールを作るとスムーズです。
- 朝の光を浴びる: 朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を部屋に入れましょう。光を浴びることで、幸せホルモン「セロトニン」が活性化し、体内時計がリセットされます。
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる: 38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスして自然な眠りに入りやすくなります。
対策③:スマホ以外の「楽しい」「安心できる」時間を作る
子どもがスマホに没頭するのは、他に安心できる居場所や楽しい時間がないからかもしれません。
スマホの利用時間を注意するだけでなく、それに代わるポジティブな時間を提供することが大切です。
特別なことを行う必要はありません。
- 一緒に料理やお菓子作りをする
- 子どもの好きなことに合わせて一緒に遊ぶ
- ペットと触れ合う など
親子で一緒に過ごせる時間を意識的に作ってみてください。
このようなリアルなコミュニケーションを通じて、子どもは安心感を持つことができ、自己肯定感を取り戻していきます。
まとめ
不登校とスマホの問題は、「依存」という言葉だけで片付けられるほど単純ではありません。
その背景には、何があるか探し、知ることも大事です。
スマホのうつむき姿勢、スマホ首には、
「自律神経の乱れ」「睡眠の質の低下」「呼吸の浅さ」といった、
深刻な体の不調が隠れています。
整体師としてお伝えしたいのは、心を回復させるには、
まずその土台となる体を整えることが非常に重要だということです。
お子さんのスマホの使いすぎを責める前に、まずはその「体のつらさ」に目を向けてあげてください。
焦らず、子ども様のペースに合わせて、心と体の両面からサポートしていきましょう!
公式ライン登録
キャンペーン実施中!
✔︎ 毎月2回の無料カウンセリング(15分)がご利用いただけます。
✔︎ LINEチャットでのご相談は無料!(回数無制限)
ごあいさつ
塾長のご挨拶

4,000人以上の体を診てきた経験 から、お子様ひとりひとりに合わせた安全・安心な整体をさせていただきます。
「姿勢が悪くなった」「集中力が落ちてきた」
「なんとなく元気がない」「疲れやすい」
そんなお悩みをお持ちのお子様・保護者様はぜひ
子ども整体 または 親子整体 を一度お試しください。
エンパワー五誠塾 吉本幸司